この記事では、下記のような疑問をお持ちの疑問を解消していきます。
 想定読者
想定読者先日久しぶりにスタバに行って来ました。
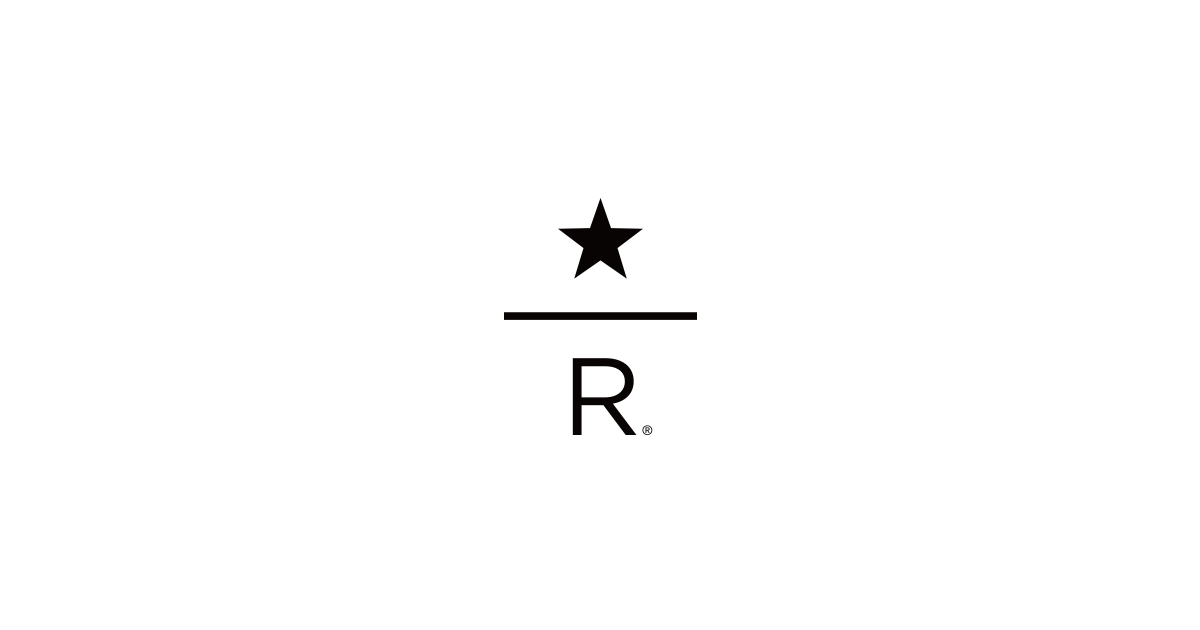
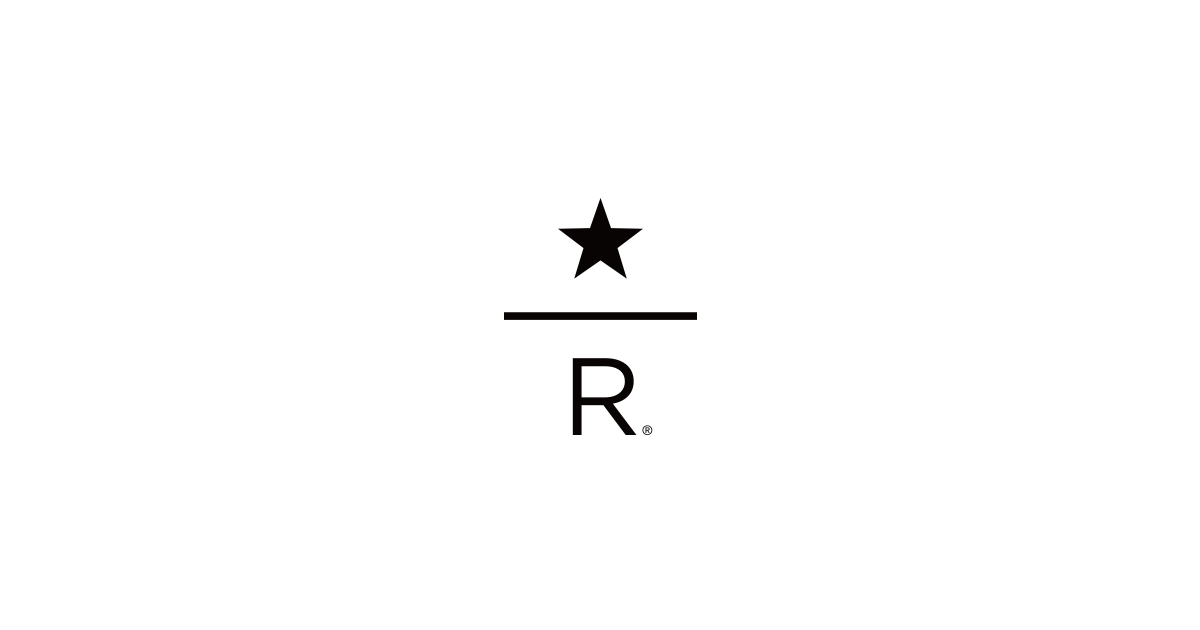
今回行ったスタバは、スタバの中でも旗艦店的扱いである、スターバックスリザーブドという店舗に行って来ました。
緊急事態宣言が解除され、やっと店内で寛げる様になり、私自身かなり久しぶりにスタバで珈琲を飲むことが出来ました。
そして改めて気付いたのですが、スタバって滅茶苦茶高いですよね。
最近は慣れてしまいもはや何とも思わなくなっていたのですが、久しぶりに期間を空けて行ってみると、やはり高い。
ただ、もう一方で気付いたのは、やはりそれでも払う価値があると感じてしまうことでした。
スタバの店内で珈琲を飲んでいると、やっぱりスタバは居心地が良いなぁ、感じるのです。
そして、今回「何が居心地の良さを生み出しているのだろう?」とと改めて観察してみて、とあることに気付きました。
今回は、2ヶ月振りにスタバに行って気付いたスタバの差別化戦略と、僕たちががそこから何を学べるのか、についてお話ししたいと思います!
何故スタバは居心地が良いのか?
そスタバは「お客様にとってのサードプレイスになる」という理念で店舗経営をしており、その結果、各店舗ごとにデザインは違いながらも、それぞれ他の珈琲チェーンとは違う居心地の良さを実現出来ている特徴があります。
自分は元々その話を知っていたので、まぁそんあもんか、と表面的に理解したつもりになっており、特にそれ以上考えることはありませんでした。
ただ、今回の緊急事態宣言中、スタバの代わりにファミレスや安めの珈琲チェーンに通っていたため、改めてスタバに行き居心地の良さの差を感じるようになったことで、「じゃあ具体的に何が居心地の良さの差を生んでいるんだろう?」と考えるようになりました。
今回気付いたのは以下の点です。
- ソファの座り心地が良く腰が痛くならない。
- 隣の席との間隔が広い
- 窓が大きく日光が入り店内が明るい
- マグカップの質感が良く、口当たりも良い
- 隣の席とのスペースが広く、元々ソーシャルディスタンス分の間隔を維持出来ている
- センスの良い絵が立てかけられている
- 照明がお洒落
- 店内の色調が統一されている …等々
流石スタバ、全部が一流!と思われるかも知れませんが、ふと思ったのは、「個々の要素の差は大したことないんじゃないの?」ということです。
スタバリザーブドは全てがちょっとずつ違う
例えば、マグカップ一つを例にあげるてみると、普通の珈琲チェーンは、色気の無い白いただのマグカップだったりしますが、スタバリザーブドはオリジナルの黒いマグカップで、これがやたらと質感が良いんですよね。
口当たりも良く、つい家用にも買いたくなるレベルです。ただ、他の珈琲チェーンも少し投資すればマグカップを替えること位簡単ですよね。
やればいいだけなので。ソファーについても同様のことが言えると思います。
ただ、スタバリザーブドはこういった一つ人つの差を積み重ねることにより、結果として、他の珈琲チェーンが太刀打ちの出来ない居心地の良さを提供出来ているのです。
高級ブランドは何故何倍も高いのか?
この「小さな差を積み重ねる」というのは、実は高級ブランドの服も同じ話だったりします。
例えば、高級ブランドのレザーバッグと安いブランドのレザーバッグの違いは、皮が違うというのは勿論ですが、加えて縫製の丁寧さや、皮の貼り合わせ部分の処理、金具の質感等々、一つ一つは少しの差なのですが、その小さな差の積み重ねが高級ブランドの製品としての質感を生み出し、結果として何倍もする価格差の説得性を担保しているのです。
個人でも同じ話では?
翻って、これって個人の仕事でも全く同じ話なのではないか、と思った訳です。
私はIT業界でコンサルタントをしていますが、コンサルタントにも高いコンサルタントと安いコンサルタントがいます。
その差は何なのでしょうか?勿論、ベースには頭の良さや知識の量があると思うのですが、結局コンサルティング業もサービス業なので、お客様への提供アウトプット、つまり発言や、ドキュメント、ファシリテーション、それぞれのポイントポイントの差の蓄積なのではないか、と思うのです。
最後に
「神は細部に宿る」という言葉がありますが、逆を言えば、「優れたものは優れた細部の積み重ね」によって成り立っているとも言えるかと思います。
自分も、ちょっとした努力を積み重ねるより、一発逆転を狙いたいと考えてしまうのですが、仕事のサービスの品質を上げたい、顧客単価を上げたい=給料を上げたい!と思うのならば、改めて自分のサービスを分解して、それぞれの要素の一つ一つ一つを「少しずつ」改善するのが、結果として圧倒的な差別化要因を生み出す最短の道なのではないかな、と思った次第です。








